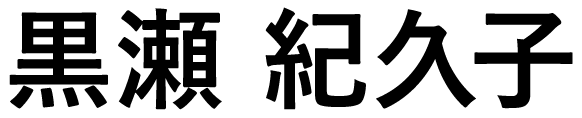闘ったり、幸せを噛みしめたりと、独り相撲をとっていたような演奏活動の中で、しばしば私は思わぬご褒美を頂戴した。 それは周りから受けた思いがけないリスペクトだった。 行く先々で人々が身に余るリスペクトを惜しみなく与えてくれた。 最初に驚いたのは、まだ私がピアニストの卵にもなっていない高校生の時だった。 コンクールに入賞しただけで、周りの先生方の態度は一変した。 一生徒に対するそれとは違って、先生方の私への対し方は、大人に対するそれだった。 体育なんかしなくてもいい、手を大切に。 試験なんかどうでもいいから、という具合だ。 ただ、当時の私はそんな自覚すらない、普通の高校生だった。
ヨーロッパに行って勉強を始めると、ヨーロッパではいかに芸術家というものが特別な存在であり、最も尊厳を与えられている職種だと考えられているかが、日を追うごとに感じられるようになった。 どこに行っても私は大切に扱われリスペクトを受けた。
それは、私という人間に対するものではなく、ピアニストへの道を歩いている私への賛辞であり激励だった。 更に言うと、私に向けられていたのは、芸術そのものに対するリスペクトに他ならなかった。
このリスペクトが私にもたらしたものは大きかった。 何よりも嬉しかったのは、このリスペクトを通して多くの他分野の方々との出会いがあったことである。 文学者、神学者、建築家、画家など、芸術家や学者が多かったが、中には医師や教育者もおられた。 皆さん、私を一人の芸術家と見なし、私も相手を一人の人間としてではなく、それぞれの職業人と見なし、その前提に立って私達は話をした。
不思議なことに、こういった方々との語らいは、ほぼ同じような経過を辿り、我々をとても興奮させるものだった。 共有するものの無いはずの他分野であるにもかかわらず、そこには同じ思いや手法、試行錯誤の数々があった。 それぞれが異なった道を登山して同じ頂上に辿り着き、同じ景色を見ているようだった。 そしてそのことは、深い井戸を掘るように道を進めば、いつか底を流れる同じ真水に行き着くこと、それぞれが掘り進んだ末に現れた真水は地下茎のように繋がっていて、それが真実の水であることを示していた。
この数々の出会いが私の人生をどれだけ豊かにしたことだろう。 50年の歩みのもたらした有難い恵みだった。